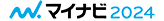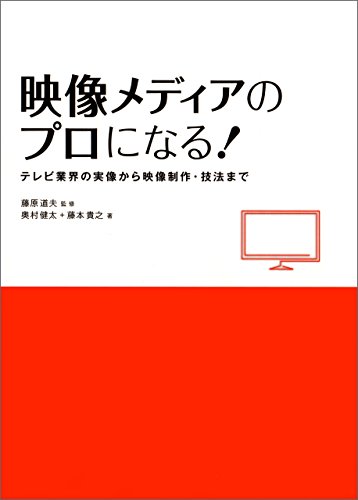「震災・・・本当に“怖かった”こと」
ない。
なにもない。
そこは数百を超える人々の、活気あふれる生活があった場所のはず、だった。
が、僕の眼前に広がっていたのは、瓦礫の山、山、山。
まるで空爆を受けたかのような・・・、そう、まさに戦場さながらの光景だった。
殆ど原形を留めていない家屋。
ビルの屋上に乗り上げた船。
デコボコになって、ぺしゃんこに押しつぶされた車。
子供がおもちゃのブロックで遊ぶのに飽きて、放り出したようにも見えるビルの数々。
全てが、滅茶苦茶に破壊されつくしていた。
宮城県・石巻市。
死者2964人、行方不明者約2770人。住宅約2万8千棟全壊。(5/20現在)
地震という、そして津波という、人知を超えた自然の脅威をまざまざと見せつけられた僕は、ただそこに立ち尽くすことしかできなかった。

***
新潟県中越地震、スマトラ島沖地震(共に2004年)など、数々の震災や津波の現場を取材してきた。もちろんそれ以外の現場取材も含めて、テレビディレクターとして経験は豊富な方であるという自負がある。
新潟では震度7を記録した町を目指し、豪雨の中を飴のようにひん曲がった道なき道を何時間も歩いて、被災者の声をいち早く取材したし、スマトラ島沖地震では、死体がゴロゴロと転がる地獄のような現場も取材した。必死になって行方不明の家族を探す父親、母親の想いにも触れた。
そんな「極限状態」とも言える現場を「踏んで」いたのにも関わらず、今回の現場では本当に足が震えてしまった。いや、竦んだ、と言ってもいいだろう。
これは比喩表現でも何でもなく、本当にガクガクと震えていた。
自分の目の前の光景が、かつて足を運んだことのある石巻市と同じだと、俄かには信じられなかったということなのだと、今では思う。
しかし、現場を見た瞬間、頭の中は真っ白になった。
恥を承知で告白すると、何を取材すれば良いのかも思いつかなかったし、全身から力が抜けて、一種の虚脱状態に陥ってしまったのも事実だ。
いつもの自分ではないような頭と体が何とか動き出したのは、その光景を目にしてから10分ほど経過したあとだっただろうか・・・。
このあと僕は青森県をスタート地点として、何者かに爆撃されつくしたような三陸海岸沿岸500キロを延々と取材し続けることになるのだが、その話は、また別の機会に譲る。

***
こういった大災害の時に見えるもの・・・、それは人間の「本性」だと常々思う。
危険が迫っているにも関わらず、警報を鳴らし続けた、など
自分の身を犠牲にしてまで他者の命を救う・・・。
そういった「美談」は見る者、聞く者を感動させるし、新聞・テレビで毎日のように繰り返し報道され続ける。
しかし、なかなか報道されない「本性」もある。
浅蔵角子さん(仮名)は、そういった人間の「本性」に恐怖した一人だ。
石巻港のすぐ近くに住んでいた浅蔵さんは、あの日、命からがら津波の猛威から逃れた。奇跡的に家族全員の命は助かったものの、津波は浅蔵さん一家から新築の家を奪っていった。
周りの家が殆ど跡かたもなく流された中、1階部分はボロボロになったものの、2階部分にはかろうじて人が入れる状態だった、「新築」の浅蔵さんの自宅。どこに避難していいかも分からない中、その夜は、かつて2階だった場所で一夜を明かすことにしたという。
3月11日、まだ東北は冬。
その日も寒い夜がやってきた。
しかも昨日までとは違う、完全なる、闇。
電気もガスも水道も、もちろん食べる物もない。
ひもじく、不安な夜を過ごす浅蔵さんの耳に聞こえてきたのは、
「ガシャン!ガシャン!」
とガラスを割るような音だった。
いつもと違う、静かな夜だけに、否応にも耳は惹きつけられる。
異様な物音が近づいて来る中、時折笑い声のようなものも混じっているような気もしたという。
開け放たれた窓から、暗闇にじっと目を凝らす。
目が慣れてきたのか、うっすらと何者かの姿が浅蔵さんの目に飛び込んできた。
バールを手にした3人の無法者たち・・・。
その瞬間、浅蔵さんは全てを理解し、そして戦慄した。
自分と同じ被災者が、これまた同じ被災者の家を荒らして回っているのだ。
誰もいない家々を物色して金目のもの等を漁る無法者たちの目には、狂気が宿っているようだった、と浅蔵さんは語ってくれた。
「見つかったら殺される!」
津波から助かったのに、ここで命を落とすことになるのか・・・そう、恐怖に慄いたという。
幸いにも、無法者たちは浅蔵さん宅に侵入することはなかったというが、再び夜が明けるまでの数時間が、無限にも感じられたであろうことは想像に難くない。
「人間、極限状態になると、他人のことなんてどうでも良くなるんですよ。
あれは、もしかしたら私の姿だったのかもしれませんし・・・。」
浅蔵さんの言葉が、胸に響く。
***
自分が同じ極限状況に置かれた時、狂気に走らないという保証があるのか。
そう、自分に問いかけてみた。
もちろん答えは出ない。
いや、出せようはずもない。
今回の東日本大震災の取材が、
自分という人間が何者なのか、
テレビディレクターとして何が出来るのか、何をするのか・・・。
そう、何度も何度も、自問自答を繰り返す旅になろうとは、
この時はまだ想像だにしていなかった。
文責:メディアアーツ事業部 奥村健太