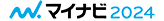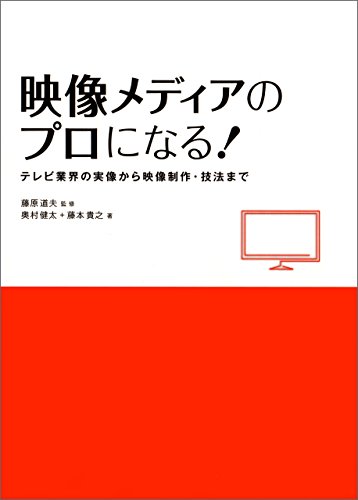『歴史の証言者』(後編)
(前編 Episode15 より続く)
「津波てんでんこ」。
三陸を取材していると度々耳にする、妙に印象深い言葉がある。
津波が来たら親兄弟にも構わず、てんでバラバラに高いところへ
逃げよ、という意味だ。
津波のスピードは僕たちが想像している以上に速く、
「来た!」と思った瞬間には津波に呑みこまれてしまうらしい。

(岩手県宮古市・田老湾。全てが破壊しつくされ、流された。)
とにかく生き延びるために、一族の全滅を防ぐため、
一人でも多くの子孫を残すための、三陸の海に生きる民の知恵だ。
今でも避難訓練の際には、「津波が来るぞーー!」と大声で叫びながら
逃げるように、逃げる一人ひとりが「津波警報」になるように、と
教えられている所も多いのだという。
三陸の地で被災者の声を拾い続けていた僕が、
この岩手県宮古市田老地区で出会ったひとりのおばあちゃん。

赤沼ヨシさん。
大正6年10月26日生まれの、93歳だ。
何かと不自由な避難所暮らしを強いられているものの、至って元気で明るい。
昭和8年の大津波の後と比べれば、天国のような暮らしだと朗らかに話す
姿が印象的だ。
それもそのはず、聞いて驚いたのだが、78年前は救援物資もろくに届かず、
雪が降り続く中で、掘立小屋を建ててムシロに寝ている人も多かったという。
食べる物も殆どなく、ごく稀に手に入る握り飯も寒さのためにカチコチに凍り、
また着る物もなく、ただひたすらに救援を待つ日々。
遺体が片付けられることもなくあちこちに転がり、数少ない食料品などを
人々が奪い合う光景は、まさに地獄のようだったという。
ヨシさんはこの田老の地で生まれ育ち、また父・堀子丑松さんは、
明治三陸大津波の数少ない生き残りとのこと。
首筋がチリチリするような不思議な感覚・・・。
【凄い人に出会ってしまった!】
・・・そう、テレビディレクターとしての勘が告げる。
「その時は、お昼を食べとりゃした。お昼さ、夢中になって食べとるところに、
どーんというように盛り上がるような、横揺れに・・・
立てないから四足になって玄関まで行きゃーした。
変な地震だなぁ、とその時は思いやして、慌てて玄関に出りゃーした。」
その日、ヨシさんは遅めの昼食を一人で食べていた。
午後2時46分。
時計の針がその刻を指した瞬間から、ヨシさんは再び地獄の淵を覗くことになる。
高齢に加えて、方言もきつい。
何を意味するのか分からない言葉も多く、またなぜか廓詞のようなものが
混じっていて、非常に聞き取りづらかったものの、そのひとつひとつが
とてつもない価値を持っている事は十分に理解できた。
僕は喰らいつくようにペンを走らせ続ける。(もちろんカメラは回っている)
「前の昭和8年のね、津波のようたれば、第一波が来て、それがまた引いてから
第二波が来たんでござんすが、今度の津波は一波も二波もねぇ。
海が盛り上がったみたいに来んでござんますもんで・・・
引き波も何にもないような・・・」
一言、一言振り絞るように語る、93歳の証言の重み。
「わだし、一生懸命走って10メートルも行かないうちに、ガリガリガリって
音がして後ろを向いたら、波が防潮堤の上を3メートルだか、4メートルだか
乗り越えて、波の上がキラキラ光りながら、こっちに来んだもん。
昭和8年の津波の3倍はあるってピンときたでござんす。
それから一生懸命逃げた。押し車を押して・・・。
でもその車がいうこと聞がねぇ。」

(赤沼ヨシさん(93)の押し車)
今回の津波がいかに巨大なものだったか。
昭和8年時のそれの3倍はあったとヨシさんは語る。
もちろんそれは正確なものではないのだろうが、実際に2度の大津波を
体験しているだけあって、言葉に迫力と説得力がある。
波というより、「のっ、と」海が浮き出てきたような感じ・・・
そう何度も繰り返すヨシさんは、逃げながら不思議なことに気が付いたという。
「昭和8年の時もその通り。誰も津波だ!という人は一人もいないでござんした。
みんな無我夢中で山に登るんでございます。もう夢中になって声も出ない。
津波で逃げっ時は、本当に誰もみんな何も言わないでござんすよ。
隣の人も呼ばないでござんすよ。自分たちの命を守るのに一生懸命で。
誰も津波だー、という人はないござんす。今度もその通りで・・・。」
津波てんでんこ。
大声で叫びながら逃げるようにと訓練されてきたにも関わらず、いざとなると
言葉もなく、ただ黙々と逃げるしか術がなかった田老の人々。
さらに過去の津波の恐ろしさを知らない人々の中には、のんびりと立ち話を
していてそのまま帰らぬ人となったケースも多かったという。
さらに問題なのは、田老地区の津波警報が鳴らなかったのではないか、
ということ。
「津波だ、という警報が鳴らなかった。
逃げる時にサイレンが鳴ってくれたら、人がもう少し助かったんで
ねぇだべな・・・って。
なんぼすごい防潮堤を造ったって、今度の場合、あんまり人の命は
救えなかったでござんすべ。
だから、やっぱり警報だけはしっかりしてもらえれば、もっと人が
死なないで済んだのでは・・・。
警報は一人残らず逃げ切るまで鳴らしてもらいたいでござんす。」
地震や津波で警報装置が故障したからなのかどうか理由は定かではないものの、
今回の取材では津波警報を耳にした人に出会うことはなかった。
行政に問い合わせてみると、警報は7回鳴ったとの記録はあるものの、
本当に鳴ったかどうかは分からない、という回答を得た。
いずれにせよ、あまりの恐怖に言葉を発することのできない住民に代わって、
早く逃げろと呼びかける津波警報の重要さを、ヨシさんは説く。
訓練はあくまで訓練。
想像を絶する事態に巻き込まれた場合の人間の心理状態までをも想定し、
強大な地震や津波にも負けない警報装置を作り、最後の一人が避難し終わるまで
警報を鳴らし続ける。
2度の大津波を生き延びた人間の言葉に、田老地区だけにとどまらず
日本全国の行政機関は耳を傾けるべきだと思う。

(一帯に住宅が並んでいたが、今では瓦礫の山・・・)
インタビューは休憩を挟みながらも半日以上に及んだ。
跡形もなく無くなってしまったヨシさんの家(があった場所)の前で、
最後に僕は、散々悩んだ挙句に、こんな質問をしてみた。
—またここに住みますか?
ヨシさんの目が潤む。
聞いてはいけない質問だったのかもしれない・・・後悔の念がよぎる。
しかし、ヨシさんは力強く僕の目を見据え、こう切り出した。
「生まれた里で、生まれ故郷で終わりたいと思っておりんす。
100歳まで生きたって、あと7年しかないでござんす。その人生を
どうやって暮らしていくか・・・。それまでにこの田老がどう復興すべか、
どのように変わっぺか、それも見ておきてぇす。やっぱり故郷は
捨てられないでござんす。」
その時、ヨシさんの脳裏には、昭和8年の大津波から力強く復興した、
かつての田老村の姿が蘇っていたに違いない。
また再び、全てを失い、何もかも無くなってしまったけれども、この田老は
再び元の姿に戻ることが出来る、そう確信していたのだと思う。
***
被災地を取材していると、批判的な目で見られることも多い。
家や肉親を失って苦しんでいる人々を映すことに意味はあるのか。
根掘り葉掘り、当時の状況を聞くのは野次馬と一緒ではないのか。
さらに興味本位の取材は止めてほしい、と言われたことも一度や二度ではない。
テレビなんてどれだけインタビューに答えても、どうせ使うのは数秒なんだろ、
と面と向かって言われたことさえある。災害救助やボランティアの人たちと違って、
僕たちは招かれざる客なのだ、と感じることが多々あるのも事実だ。
しかし、ヨシさんのような2度の大津波を生き延びた人物の貴重な証言・・・
歴史の証人と言っても言い過ぎではないと思うが、そのいつかは
失われてしまうであろう、彼女の記憶をカメラで記録することこそ、
テレビディレクターとしての使命であり、
マスコミに携わる人間にしかできない仕事なのだと思う。
ヨシさんだけではない、未だ8万人以上いる避難民の方々の「記憶」を
出来る限りたくさん「記録」し、「放送」すること。
そしてそれを教訓に、また必ず来るであろう津波の被害を最小限に抑えること。
それが僕の好きな三陸に対してできる、最大限の恩返しなのだ。
あれから3ヶ月が経ち、テレビや新聞紙上で震災関連のニュースは
減り続ける一方だ。
永田町の老人たちの醜い権力争いや、少女たちの「総選挙」を面白おかしく
大々的に取り扱うのも良いだろう。
そういったニュースを好む人たちがいるのも事実だからだ。
テレビは高尚であれ、と講釈を垂れるつもりはさらさらないが、
阪神淡路大震災の際には、その直後に起きた地下鉄サリン事件報道がテレビを
「ジャック」し始めた途端、義援金が集まらなくなったと聞く。
「3・11」を忘れないためにも、三陸の人々の「記憶」を「記録」することを
出来るだけ長く続けること。
それが復興を支え、また僕たちが再び、美味なる三陸の海の幸に
舌鼓を打つことができるようになる、一番の早道なのではないだろうか。
(了)